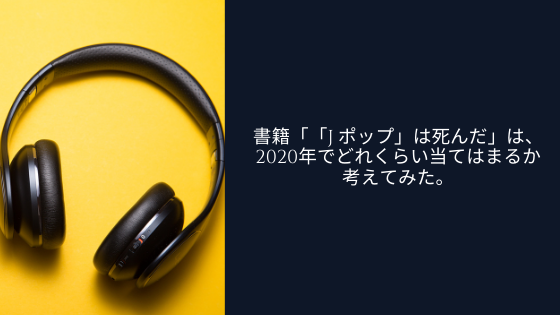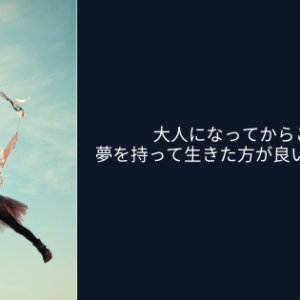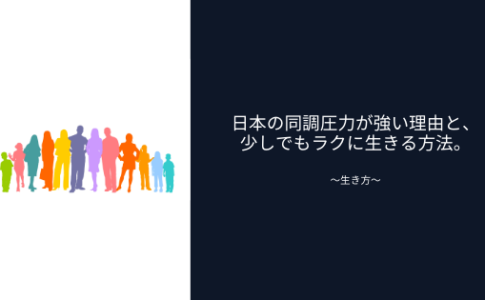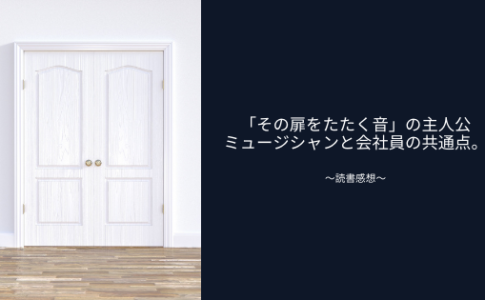昨日、ジャーナリストで音楽評論家である烏賀陽弘道さんの本「「Jポップ」は死んだ」を読みました。
2017年に出た本で、日本の音楽ジャンルの総称である、いわゆるJポップがどうやって世の中で存在感を出してきたのか、
そして2017年時点でどういう縮小の仕方をしているのか、ということが書かれている本です。
毎週図書館で1冊本を読もう!ってことで、たまたま手にしただけなのですが、内容がわかりやすいのでざっと流し読みするなら20分くらいで十分のボリューム。
2017年発売のこの本で言われていたことが、今どうなの?ってことに興味が湧いたので、今日はその話を書いておこうと思います。
いつの時代も本は良いですよね、過去と現代を言葉で結んでくれるようです。
わたしは電子書籍や紙の本で毎日何かを読んでいます。
「「Jポップ」は死んだ」の主な話の流れ
目次の詳細は本を開いてみてもらうこととして、話の流れとしては大枠こんな感じです。
- 日本人はどんな場所で音楽に触れるのか?
- インターネットの登場は、音楽業界をどう変えたのか?
- 1990年代後半以降の少子化時代と音楽業界
- これからの音楽の届け方
- ネット時代の音楽家の生きる道
この5つについて、それぞれ2017年に書かれていたことと、2020年の終わりにさしかかるあたりの今の状況、どれくらい当たってたの?
というのを、インディーズミュージシャンの一人であるMIMOGYの超私見もどっぷり交えながら書きたいと思います。
興味のある見出しだけ読む形でも良いかと…!
1.日本人はどんな場所で音楽に触れるのか?

前半は、日本人はどんな場所で音楽に触れるのか、ということについて書かれていました。
みなさんは最近だとどこで、あるいは何を使って音楽に触れますか?
おそらくほとんどの方がYouTubeではないでしょうか?
SpotifyやApple Musicの方もいますかね。
わたしも、新しい音楽だけでなく過去の楽曲を探すときもほぼYouTubeから探します。
ただ、この流れってインターネットの登場以前はなかったもの。
その前はどうやって出会っていたのかというと、その機会のひとつがライブハウス。
ちなみに、ライブハウスという言葉は日本語特有で、海外ではほとんど使われていない言葉です。
海外だと飲食店やカフェのBGMが生演奏、という形で音楽を聴けたり、居酒屋やバーでバンドたちが演奏する光景はよく見るところ。
音楽は食事やお酒と相性が良いですが、生演奏とも距離が近いのがアメリカやイギリス、オーストラリアもそんな気が。
ちなみに、ニューヨークで路上ライブをするとすぐにみんなチップ入れてくれて、その日の生活費くらいはすぐに集まります。前行ったときやりました。
日本だと通行人に通報されて警察に連れていかれる可能性があります。
あと、女性が路上で歌っている場合はおじさんがたくさん集まってくるかもしれませんねー。
そもそも道路交通法違反で厳しいので、日本ではほぼ路上ライブはしたことがない…。
日本では、音楽が生で鳴っているという環境に慣れていない、あるいはそもそも音楽の楽しみ方を知らない、
音自体うるさく感じる人が多く、人も密集していて空間にも余裕がないので、
いろんな意味で浸透していかないんだろうなと、いろんな国に行って痛感しました。
話は逸れましたが、楽しみたい人だけが集まるアンダーグラウンドな環境がライブハウスだし、ライブハウスは音楽演奏のためだけに使われる会場なんですよね。
ただ、カフェでライブができるような形態は、ここ10年くらいで日本でも増えてきたそうですよ。
わたしも演奏はカフェバーやライブレストランがメインです。グランドピアノがあると最高。
この本の筆者も、ライブハウスという日本特有の場所について書いていて、
- 演奏する側にノルマ制を課すことで安定した経営を実現している
- 海外はお金をもらえばミュージシャンだが日本では扱いがちがう
- カフェがいわゆる「ライブ」を聴けるライブハウスである
ということに触れていて、ここ最近だとライブハウスはお客さんを入れることよりも演奏動画を録るために使う演者も増えている印象だと書いていました。
2017年時点ですでに起きていたことは、2020年の終わりに差し掛かる今も、大きくは変わっていない気がします。
コロナでライブハウスも減っていますが、そもそもの時代の流れもあるのかもしれませんね。
これからは、生演奏の音はもちろん、良い演奏動画を録れるかどうかという意味で、撮影や録音のスペックや配信ライブ機材があるか、
それらができるスタッフがいるかどうかでライブハウスを比較する時代が来ると思います。
わたしも今後に向けて良い会場探そうっと…!
他に筆者はフェスの台頭にも触れていて、YouTubeは無料、ライブは有料という流れが起きているという話もしていましたが、
そのライブ自体はコロナで新しい形を模索し始めたのが2020年だなと感じるので、詳細は省略します。
2.インターネットの登場は、音楽業界をどう変えたのか?

インターネットがない時代なんて、もう考えることが難しいなぁと感じますが、昔はどうやって音楽に出会う仕組みが作られていたの?という話も書かれていました。
ちょうどこんな話をしたあとだったので興味が。
娯楽が少なくアナログだった時代の音楽の聴き方をいろいろ聞いたんだけど、
・BGM曲名をお店のマスターに聞く
・有線なら電話で曲名問い合わせ
・数千円のレコードたちを一枚一枚買って聴き漁る今とは全然違う、発掘の楽しさと作品の味わいを聞いて、少し不便な時代ならではの良さを感じた。
— MIMOGY-ミモギィ-@パラレルキャリアなシンガーソングライター (@MIMOGYSOUL) October 29, 2020
ひとつはラジオですが、この本によると、Jポップという言葉はJ-WAVEから出てきたらしいですよ。
時期は1988年だとか。
すべての邦楽の象徴みたいな言葉。言葉の力はすごいですね。ビッグワードを産んだら勝ち的な構図ありますよね。
80年代から90年代にかけては、まだおそらくみんなテレビを見ていたし、新聞を読んでいたし、
同じようなニュースを見ていたし、ドラマを見ていたから、主題歌で曲やアーティストを知ることも多かった。
「え、なんで知らないの!?昨日テレビでやってたのに!」みたいな言葉がまかり通る時代だったと。
マスメディアとタイアップがヒットを決める、というのが鉄板の構図だったそうですよ。
が、1990年代後半からのインターネットの登場で、みんなが同じものを見て追いかける時代は終わり、ニュースへのスタンスも変わった。
SNSが出てきて、つながっている人たちの周りで起きていることが「ニュース」になるようになったとのこと。
スマホが本格的に世の中に出てきたのは2007年で、ネットに加えてスマホが普及すると、この流れは加速を避けられないですよね。
一人一台一画面、なら同じ場所にいても全員自分の興味関心のみで世界が完結してしまうし。
2017年から3年ほどたって、2020年は動画アプリもSNSの仲間入りをしているし、みんな発信者になれる時代になっていて、
より自分とつながるものへの興味関心が向くようになっている印象です。
逆に言えば、興味がないものに興味を持つきっかけについては、つながる人が新しい何かをやったり知ったりするときっかけができるけど、そうでないなら永遠に知らないままかもですね…。
音楽を届ける側としては、興味を持ってもらうきっかけづくりもちゃんとしないと、とてもじゃないけど継続していけないですね…大変だー
ブログでもいろんなことを発信していこう!
3.1990年代以降の少子化時代と音楽業界

2の話とこの3の話はセットだなぁと思っていて。
日本ってすごい少子化なのはなんとなくご存知かもしれませんが、将来の人口推計を見ると、2025年以降は70万都市が毎年1つ消える計算です。
かつてのJポップは、産業としては団塊ジュニア世代をターゲットにしていて、分厚い若者層に何を売るか!?みたいなことを必死に考えていたそうです。
でも今若者層分厚くないからなー。人口が分厚くない。ただ高齢者向けだと多少は分厚くなると思う。
Jポップは若者向け、というのから、音楽業界はずっと抜け出せていない、と筆者は書いていました。
最近編曲関連で作家の方と話す機会がけっこうあるのですが、その方もJポップは20年間変わっていなくてほぼガラパゴスだと言っていました。
人によって感じ方は違うと思うけど、Aメロを聴くと大抵流れの予想がつく、という意味ではずっと変わっていないのかもしれない。
また、タイアップとセットで売るという形に頼っていると、タイアップに選ばれないような知名度はないけど良い!というアーティストを育てる余裕がなくなり、
中間層はいなくなって売れる層と売れない層で二極化していくとのこと。
タイアップアーティストは企業が決めるから、売れてないアーティストを選ぶ企業があまりいない、というのが理由だそうな。
ちなみに、高齢者向けとするとカラオケ市場はアツいらしいですよ。
ただ2020年はコロナでカラオケもクラスターになりやすく避けられるようになったので、今後はどうなるんでしょうか。
おうちカラオケですかね。マイクは必ず除菌でマイマイクの方が良いですよ!
4.これからの音楽の届け方

音楽業界の話をしても、正直フリーで活動しているわたしのようなアーティストとは規模感が違うのですが、フリーの人にも役立つことも書いていました。
それは、音楽を制作するコストはどんどん下がっているから、自作リリースに大金はいらないという話です。
昔は機材ひとつひとつが高く、スタジオ代も高く、アルバム制作するにしても渡航費含め海外に行った方がかえって安い、という時代もあったそうですが、
今は30万もあれば一通りの機材はそろう時代ですよね、とのこと。
わたしも家で制作できるように札幌にUターン移住して2年目ですが、家で制作できる環境があれば自作リリースはしていけるなぁと思います。
あとはネットは光回線をひけば、配信ライブや大量の音楽データのやりとりも問題ないですよね。発信活動ももちろん可能。
環境の変化に合わせて自分の環境も変えることができると良いです。
5.ネット時代の音楽家の生きる道

本の終盤では、ネット時代の音楽家について書かれていました。
今まで書いてきた話を振り返りながら、これからの音楽家は「スモール〜ミッドレベルの収益構造を覚悟せねばならないだろう。」と述べています。
- フルタイムミュージシャンは成り立ちにくくなるかもしれない
- パートタイムでミュージシャンをやりつつ、活動する
- CD製作費や演奏ツアーのために資金はクラウドファンディングで集める
そういった形での活動が増えていくのではないか、そうせざるを得ないのではないか、という話でした。
実際2020年終盤の今でも、そういった活動の仕方をしている人は多いのではと思います。
わたしもパラレルキャリアという形でミュージシャンをしているけど、時代を先取りしたのかもしれない…!w
これからは複数の仕事をするのは当たり前になる時代がやってくるはずって、音楽活動を始めてすぐの頃から思っていたけど、案の定だなぁと感じる。
これからは自分のリスクは自分でヘッジする時代。
でもそれはつらいことではなくて、自分でコントロールできることを増やすことにもつながりますよね。
— MIMOGY-ミモギィ-@パラレルキャリアなシンガーソングライター (@MIMOGYSOUL) October 27, 2020
コロナでいろんなこと前提が崩れて、もう一度立ち止まって考えている人も多いと思うけれど、どうやって音楽とともに生きていきたいかとセットになりますよね。
ちょっと考えたい人向けにはこんな記事も書いているので良かったらどうぞ。
これからは、インディペンデントな活動で続けられれば幸せ。
わたしは音楽活動を始めたのが社会人になってからで、コンサルティング会社で働きながらだったこともあって、現実をちゃんと見てから始めました。
本で書いていることはほぼ当たっていると思うし、2021年以降はコロナだけじゃなくAIもどんどん出てくるから音楽はより影響を受けると思う。
こういうことを考えているのは、全然アーティストっぽくないかもしれないんですが…。
ぼんやり夢を見続ける、ってよりは、どうやったらやりたいことを続けられるのかをちゃんと考えていきたいなと思って、音楽活動するか迷ったけど結局始めてみて、
この前活動7年目に入りましたが、やってみてすごい良かったと思ってます。
これからまだやりたいこともたくさんあるし、作りたい曲がたくさんあるし、生み出したい世界がたくさんある。
時代の変化に負けないで、自分なりに適応して、インディペンデントな活動で自由に続けていく人がどんどん増えていけばいいと思う。
インディペンデントで幸せな活動を作っていけたら、それはそれで一つの良い形。
これって、実は音楽活動に限らないんですよね。
全ての仕事や働き方に当てはまる話だから。
参考になったら嬉しいです。