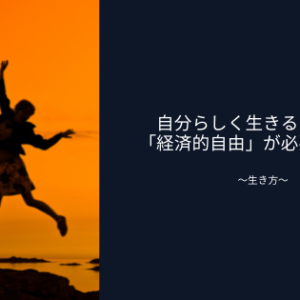毎日寝る前の習慣でいろいろな本を読むのですが、この記事では最近読んだ小説「その扉をたたく音」が面白かったので、読書感想を書きます。
2019年本屋大賞受賞作家でもある瀬尾まいこさんの青春×音楽小説。
音楽小説はなぜ青春と相性が良いのだろうか、とこの本を読んで感じたのと同時に、音楽は年代を超えてコミュニケーションできる素敵なものだなと改めて思いました。
わたしもフリーのシンガーソングライターで、この本に出てくる主人公と同じような感情になったこともあるし、一方で会社員でもあって、やっぱりこの主人公の気持ちがわかるなぁ、と思ったので、後半ではその理由もあわせてご紹介します。
本が好きな方や、おうちタイムのお供を探している方は、ぜひ最後までお読みください。
大まかなあらすじ
主人公は、29歳無職の自称ミュージシャンの男、宮路。
舞台は老人ホーム「そよかぜ荘」。
毎週金曜日のレクリエーションの時間に、たまたま宮路がギター弾き語りをしに行ったのをきっかけに、物語が始まります。
宮路はバイトすらしていません。
親が裕福で毎月20万円が口座に振り込まれるため、働かなくてもお金が入るからです。
演奏でお金を得ているわけでもなく。
時々、今日みたいに老人ホームや病院にギターの弾き語りに行くことがある。
けれど、俺は音楽を仕事にしているわけではない。
残念ながら、演奏することでお金が発生したことは一度もなかった。
(出典:「その扉をたたく音」本文より)
一度もお金が発生したことがないのはつらいですね…。
もはやミュージシャンになりたいのか、何をしたいかもわからなくなったまま、どうしたら良いかもわからず気づけば30歳目前の宮路。
そんな彼が、自分の演奏のあとに偶然聴いたサックスの音色に衝撃を受けます。
「神様」と宮路が呼ぶその相手は、老人ホームに勤める25歳の介護士、渡部くん。
この「神様」のサックスの音をもう一度聴きたい!
という想いから、宮路は老人ホーム「そよかぜ荘」を再び訪れ、そこで個性豊かなお年寄りの方々と交流するようになります。
宮路を「ぼんくら!」と呼びつけて買い出しをさせる水木のばあさんや、ギターを弾く宮路を見て「ウクレレを教えて欲しい」と頼む痴呆症持ちのおじいさん本庄さんなど。
この老人ホームの方々と宮路のクスっと笑えるやり取りがちりばめられていて、一方で、いつかは人の命は終わるという現実も改めて認識できるようなシーンもあります。
主人公宮路が、自分に足りていなかった何かに気づき、今いる場所から抜け出して再び人生を歩むきっかけをつかむまでのハートフルストーリーです。
音楽小説なので、中盤ではサックス渡部くんとギター弾き語りのデュオをどうやって合わせるか試行錯誤しつつ、鬼練習するシーンもあったりします。
サックスとギターは確かに難しそうですね!
60年代や70年代、それ以降で誰もが耳にしたであろう洋楽や邦楽の曲もいろいろなシーンで出てくるので、音楽好きにはその点もすごく面白いのではないでしょうか。
前半で、そよかぜ荘のレクリエーションにて、宮路がこの曲を渡部くんに演奏してほしいと叫ぶシーンがあるのですが、これが実は伏線にもなっています。素晴らし!
タイトルにある「その扉」はきっと登場人物それぞれにとって違う。
「その扉をたたく音」は音楽そのものと音楽を通した人間同士のコミュニケーションなんだろうなと思いながら、1時間くらいですぐ読める良作でした。
また、わたしは演奏含めて老人ホームに行ったことはないのですが、老人ホームや介護の仕事についても知るきっかけになりました。
ミュージシャンになるきっかけで多い、コミュ障
コミュ障と言うのはちょっと誤解がありますが、宮路もこのタイプで描かれていました。
人とうまくコミュニケーションが取れないときに、音楽を通してだったら伝えられる、という経験をしたことはありませんか?
あるいは、うまく言葉で言い表せないときに、世の中で流れている曲を聴いて「今の自分の気持ちにぴったりだ!」と思ったことはありませんか?
音楽を始める理由はそれぞれですが、この小説の中では、ちょうどバンドブームの学生時代にて、「ギターを始めたら仲間に入れるかな…」と思ってギターをお父さんに買ってもらった宮路の気持ちが書かれています。
楽器が弾けたらすごいって思われるかも!
モテるかも!
って理由で始める男子中学生・高校生も多かったのかなぁ。
宮路は毎月20万円黙って仕送りしてくれるような家庭で育っているので、一般的な家庭より裕福ですが、そのせいで幼少期に「あいつは金持ってる」と思われたうえでの友だちづきあいが多かったそうです。
これは、ミュージシャンに限らずいろいろな人に起こる話かなと感じました。
純粋な気持ちで人付き合いするのが怖くなると、人間不信になります。
わたしもいろいろな経験で人間不信な子ども時代を過ごしてきているので、すごく共感してしまいました。
でも、音楽を通すと、変な利害関係もなくて、「音楽が好き」という純粋な気持ちで関われる人に出会えるんですよね。
いつしかコミュ障も少しずつ薄れていくという。
そして、人や社会とつながっていくようになります。
宮路の初めてのギター弾き語りの演奏は、「そよかぜ荘」のお年寄りたちには全く印象に残らない残念な時間でしたが、本編の後半での巻き返しは感動的ですね。
独りよがりな音楽は、どんなに上手でも誰にも響かない。
でも人や社会とつながる音楽は、誰かに必ず響くもの。
だから、音楽はコミュニケーション。
わたしはそう思っているのですが、この本でも同じようなシーンがありますよ^^
一見すると無意味で無価値に捉えられるかもしれない、けれど実際は人の心をすごく癒しているのが音楽ですが、音楽そのものだけでなく、音楽を通した人間関係も癒しになっていくんだろうなと思いました。
わたしも、音楽を通して出会った人たちに改めて感謝の気持ちでいっぱいになりました!
無職のミュージシャンと会社員の共通点を考えてみた
演奏でお金をもらえない、人生に迷う無職ミュージシャン(親の仕送りつき)。
毎月お給料をもらっている会社員と共通点なんてあるわけないだろ!と思いますか?
共通してぶち当たる悩みは、「このままで良いのかな…」という漠然とした不安です。
親の仕送りで金銭的に困っていない無職ミュージシャンも、とりあえず日常に忙殺されてお給料をもらう会社員も、現状生きるのには困っていない。
ただ、こんな悩みは共通かも。
一緒にバンドを組んでいたやつらとたまに飲みに行っては、自分との違いを見せつけられる。
仕事の不条理さに家庭を持つことのたいへんさ。出てくるのは苦労話ばかりなのに、聞けば聞くほど、自分が置いてきぼりになっていることに気づく。
(出典:「その扉をたたく音」本文より)
一緒にバンドを組んでいた友だちと自分の違いを痛感するミュージシャンも、同じ学校に通っていた友だちと自分の違いを痛感する会社員も、自分だけ置いていかれたような気持になる瞬間に遭遇するという意味では同じ気持ちになることがあるのでは?
社会に出てから時間が経つと、そのうち同期と差がついてきてなんとも言えない気持ちになったり、学生時代の友人と話が合わなくて無駄に焦ったり、そんなことは誰にでもあるはず。
自分の足で立って生きていれば、焦る必要なんて本当はないんだけど。
そういう焦りが、一時期わたしもあったなぁって、そんな気持ちになりました。
生き方に迷う人は読んだ方が良い1冊でした
「こういう悩みって、自分だけじゃないんだな」って、立場は違っても感じられる1冊でした!
そして、人とのつながりが薄くなりがちな今の時代に、血縁に限らない人との関わりや温もりを感じられるような、そんな作品でもありました。
【書評】瀬尾まいこ最新作は、人とのつながりを描いた感動の物語『その扉をたたく音』他3編(集英社ハピプラニュース)#Yahooニュースhttps://t.co/sAkMg41Yvj
— 集英社文芸書 (@shueisha_bungei) April 12, 2021
ぜひ読んでみてくださいね^^